質屋の日(7月8日の記念日)|今日は何の日
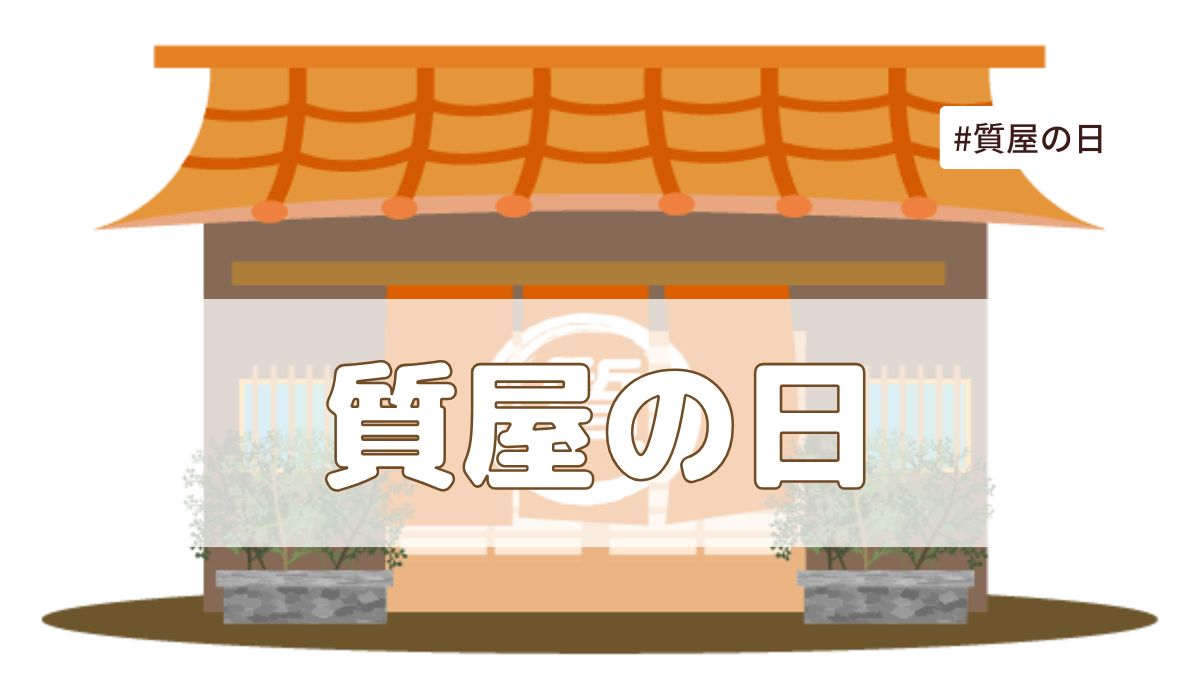
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
7月8日は「質屋の日」です。
これは「しち(7)や(8)」という語呂合わせから、全国質屋組合連合会が制定した記念日です。
この記事では、「質屋の日」の由来から質屋の歴史などで解説いたします。
質屋の日(7月8日の記念日)とは?
7月8日の「質屋の日」は、「しち(7)や(8)」という語呂合わせから質屋という業態の存在意義や役割を広く知ってもらうことを目的として制定されました。
質屋は、古くから庶民の生活に密着した金融サービスとして親しまれてきましたが、昨今ではその存在や仕組みがあまり知られていない側面もあります。
そこで、7月8日を機に、改めてその価値を見直してもらおうというのが狙いです。
関西ではひちやとも呼ばれ、一六銀行(いちろくぎんこう)と言う俗称でも知られています。
質屋の歴史と変遷
起源は鎌倉時代
質屋の原型は「土倉(とくら)」と呼ばれた機関で、鎌倉時代にまでさかのぼります。
人々が物品を担保にお金を借りる仕組みは、当時の寺院や裕福な商人のもとで発展しました。
江戸時代に制度化
江戸時代には、質屋が庶民の生活を支える金融機関として一般化しました。幕府の認可を受けた「公許質屋」は、法的にも整備されており、質物の保管や利息の設定にも厳格な規定がありました。
近代以降の変化
明治以降も質屋は庶民金融の一翼を担ってきましたが、1970年代以降、消費者金融やクレジットの普及により、利用者は減少傾向に。
しかし、現在でも「信用情報に影響を与えない貸し借り」という独自の特徴が見直されつつあります。
