2026年の秋社日はいつ?お供えする物やしてはいけないことは?
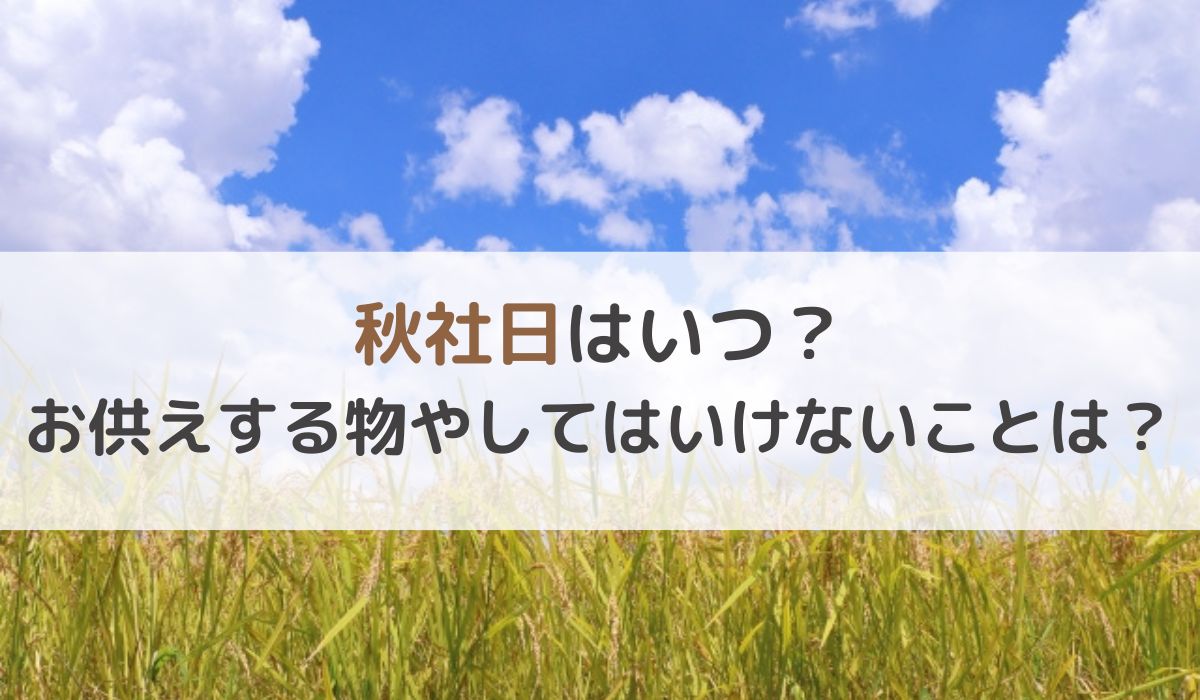
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
みなさんは、地域の氏神様などの神社で秋にお祭りが行われているところをみたことはありませんか?
秋には、社日という大切な行事があるのです。
簡単に言えば、土地の神様に日頃の感謝をしてお祀りする日のことです。
今回は、2026年の秋社日はいつなのか、お供えする物やしてはいけないことなどをご紹介いたします。
2026年の秋社日はいつ?意味と由来は?

2026年の秋社日は9月21日(月)です。
社日(しゃにち・しゃじつ)とは、「雑節(ざっせつ)」が由来とされており、土地の神様すなわち「産土神(うぶすながみ)」をお祀りする伝統行事です。
社日は「秋社日(あきしゃにち)」の他に、「春社日(はるしゃにち)」もありますので、年に合計2回あることになります。
雑節とは、日本独自の文化で、季節の移り変わりを日本の昔の暮らしと充てて考えられた暦のことです。
日本の生活文化を基盤として作られているため、今も私たちに身近な行事もあり、例えば「お彼岸」なども雑節一つだと言えるでしょう。
2回あることにも意味と由来があって、土地の神様というものは春の社日に地上にお降り(おくだり)になって人々に恵みをもたらし、秋の社日になると天の神の国へ帰ると言い伝えらえてきました。
ですから、春社日には種まきの時期と草花が芽吹くことから五穀豊穣の祈願を行い、秋社日は収穫の時期となるためその恵みの感謝を神様に捧げるという意味があるのです。
社日は中国から由来されたものだったのですが、日本の農業文化と結びつき、田畑や土地の神様を信仰する日本人の考えと共に定着し、雑節として今の社日がある訳です。
社日の決め方は、春分・秋分に最も近い「戊(つちのえ)」の日とされています。
昔は干支十干(えとじっかん)の組み合わせで暦は決められており、干支十干もそもそもは中国由来のものでした。
社日等の行事の他、昔の日本は吉日なども干支十干で読んで行動していた歴史があるので、もしそちらにご興味がある方はぜひこちらもご覧ください。
→「巳の日・己巳の日」の意味とは?違いはある?やるといいこと・いけないことは?
秋社日のお供物は何がいい?

- その年に収穫した季節の農作物
- 新米
- お酒
- 稲穂
- おはぎ
- お餅
秋社日は収穫の感謝を神様に祈るのですから、その年に収穫した農作物や稲穂、新米をお供えすると良いとされています。
お酒やお餅もその年に出来上がったものがあると尚良いかもしれませんね。
また、呼び方は違うだけで同じお菓子ですが、春は「ぼたもち」、秋は萩の花にちなんで名付けられた「おはぎ」もおすすめです。
地域によってお供えするものも違っていることもあるので、もし気になる土地があれば調べてみると面白いかもしれませんね。
お供えに肉や魚はNG?
ところで「肉や魚」はお供えしてはいけないのかというお話ですが、実際は神様にはその土地で獲れた魚などをお供えする場合もあります。
確かに仏教においては殺生を連想させるため、肉や魚のお供物は禁忌とされています。
同様の理由で神様の場合でも良くないというお話を聞いたり、そのようなことが書き記されたものを見かけることもありますが、実際は「地域によって違う」というのが正解だと考えられます。
「うちの神様はどうなのかな?」と思った方は、秋社日に氏神様の祭壇をチェックしてみてくださいね。
秋社日にしてはいけないことは?
秋社日にしてはいけないことは、
- 土を触る
ということだと言われています。
社日を決める際は、春分と秋分に一番近い「戊(つちのえ)」が社日となるという訳ですが、これが土を触ってはいけない理由と関連しています。
なぜなら、中国の陰陽五行説にちなんで「戊(つちのえ)」は「土」と関係性が深い符号であるとされているからです。
よっていわゆる「土いじり」をすると、神様を怒らせてしまうと言われているのです。
昔はこの日は農作業はお休みとされており、現代でも信仰心の高い地域は田畑の作業をやめ、ガーデニングすらも避ける風習があるそうです。
なんだか昔の人々がいかに収穫に感謝していたかが分かるお話ですね。
色々便利で効率的になった現代は何でも手に入りますが、昔は色々と自分達でやっていかねばなりません。
自然やそれを司る神々に感謝し、物を大切にする心は、今よりも昔の人の方が高かったと言えるのではないでしょうか。
まとめ
秋社日はその年の収穫を神様に感謝する意味があるので、その年に収穫できた農作物や米、餅、お酒や稲穂などをお供えしましょう。
社日は春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日を選びます。
戊は土と関連しているので、社日には「土いじり」は神様を怒らせるのでしてはいけないこととなっています。
今年の秋社日は昔の人にならって、現代人の私たちも収穫の感謝の気持ちを大切にしたいものですね。
