土用は迷信?気にしないで土いじりしても大丈夫?
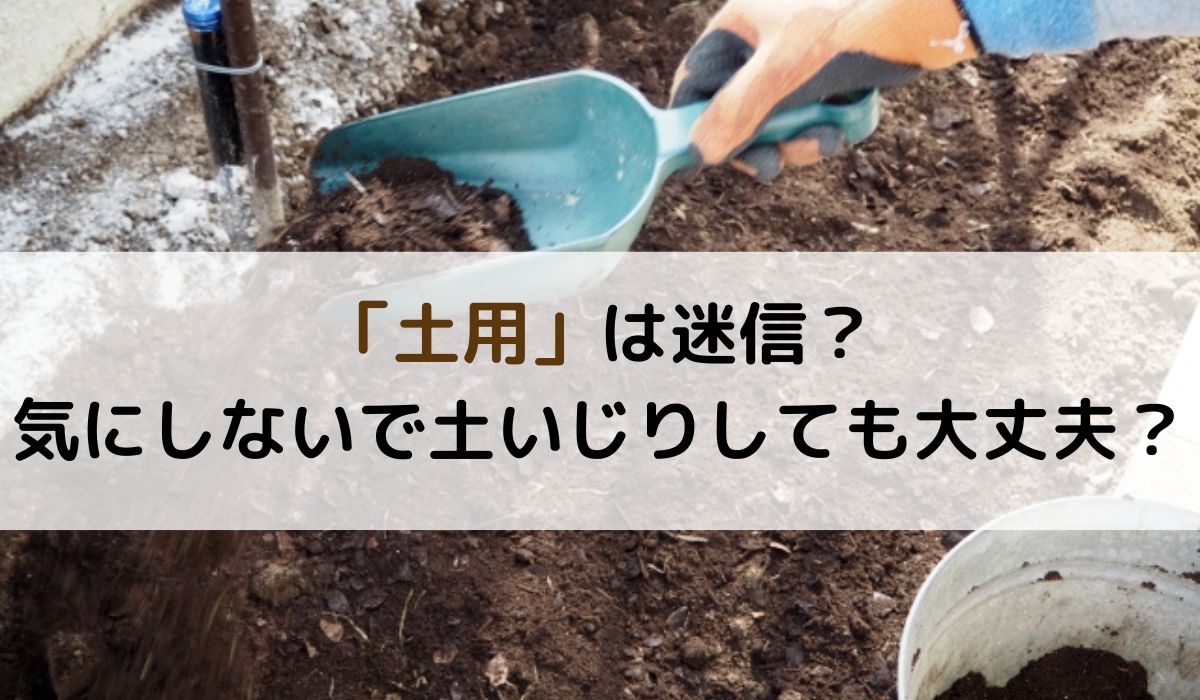
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
日本で暮らしていると必ず聞く「土用」。
うなぎを食べる日である「夏の土用の丑の日」が有名ですよね。
今回はこの土用について迷信なのか?あらためて知っていきましょう。
土用にしてはいけないことや、土いじりするとどうなるのか、現代では土用を機にする人は少ないのかなども一緒にみてみましょうね。
目次
土用(どよう)とは?
『土用(どよう)』とは「雑節」の一つの行事で「季節の移り変わり」のことです。
日本には四季があるので、季節の移り変わりである土用は4回あるということになります。
「春土用」「夏土用」「秋土用」「冬土用」となるわけですね。
そして土用には期間があります。
その決め方は立春・立夏・立秋・立冬の前のおよそ18日間が土用の期間とされているのです。
土用の最初の日は「土用入り」土用の最後の日は「土用明け」と呼びます。
ちなみに雑節とは、日本人の農業や生活スタイルに合わせて作られた独自の暦のうちの一つで、一年間で何をする時期なのかを把握するためにできたものだと言われています。
ですから、私たちに身近な行事である「お月見」や「彼岸」なんかも雑節の一つなのです。
土用の由来
日本独自の暦である雑節の一つ「土用」ですが、由来は中国の陰陽五行説からきています。
五行説というのは、この世におけるすべてのものは「木火土金水」の5つの要素から成り立っているというもの。
ですからもちろん春夏秋冬もこの5つの要素に当てはめることができ、春は木、夏は火、秋は金、冬は水と考えられていました
そして「土」はそれぞれの季節の変わり目を意味しているということなり、これが土用となったというのが由来なのです。
土用にしてはいけないこと
土いじり
- 庭仕事
- 農作業
- 草むしり
- 基礎工事
- 穴掘り
- 井戸関連
- 地鎮祭
新しい事を始める
- 転職
- 結婚
- 開業
- 引越し
など
土いじりをしてはいけない理由と由来
本当は土用は「土旺用事」という言葉でした。
土用の期間は、大地つまり土のパワーが強まり、土公神の支配によって土は安定し、次の季節に移り変われるものと考えられていました。
ですから、土用に土いじりをすると「土公神の怒りを買ってろくなことがない、悪いことが起こる」等と言われていたのです。
更にもっと細かく説明すると、土公神は季節によっていらっしゃる場所がかわるとも言われていました。
春はかまど、夏は井戸、秋は門、冬は庭にいらっしゃるとされていたのです。
これらはすべて、昔は土で造られていたものですよね。
ですから、土いじりの他にかまど関係や井戸掘りなどもしてはいけないことに含まれていたわけなのです。
新しい事を始めるのを避けた方がいい理由と由来
土用の時期は、新しいことも避けた方が良いと言われています。
これは「季節の変わり目は体調を崩しやすかったり、気候も不安定になりがちなのでやめておいた方が良い」という風に考えられているからです。
これもまた昔の人が「季節の変わり目は大事を取って体調管理を第一」としていたことが由来だと考えられますね。
土用は迷信?土いじりをするとどうなるの?
現代では土用を気にする人は少なくなっていますよね。
土用を気にして土いじりをするとどんな目にあってしまうのか?
結論としては、土用に土いじりをしたからと言って何かが起こるということは有りません。
土いじりはしても大丈夫なのです。
そもそも土用の期間は、土用18日間×4季節分=年間約72日間もありますから、いくら土用の土いじりは土公神を怒らせるためにやめておこうという習わしがあっても、農業や土木を生業にしている方々なら、そんな18日間も土をいじらないだなんて現代生活には無理です。
実際、現代においては農業や土木関係者だけではなく、土用自体を気にする方々は少なくなり、事業や家事などに影響は出ていないと言えます。
ではなぜ「土用は土いじり禁止」ということが今も引き継がれているのでしょう。
それはおそらく、「土いじり」=「仕事」であった昔の人々の教訓として残っているのだと言えます。
昔は電気なんて便利なものはありませんから、日が出ている間に仕事を終わらせようと、人々は必死で働きました。
しかし季節の変わり目は、日照時間も変わり、自律神経やホルモンバランスが乱れやすく、体調も崩しがちになります。
前の季節と同じ様に体を動かしていては、どうしても体に負担が出てきてしまうのですね。
ですから、土用のときこそ無理せず体を休め、次の季節への適応として心身ともに整えることの大切さが現代へと教訓として引き継がれているのだと考えられるのです。
土用でも土いじりOKな日はある?
実は土用の期間には、土いじりをしてもOKとされる「間日(まび)」というものがあります。
これは、土公神が土から離れ天へ返る日であるから、土を触っても問題なしと言われていたのです。
2025年の間日を以下に記載しておくので、知っておきたい方はぜひご覧ください。
2025年 間日一覧
冬の土用(1月17日〜2月2日)
間日・・・1月21日・22日・24日、2月2日
春の土用(4月17日〜5月4日)
間日・・・4月18日・19日・22日・30日、5月1日・4日
夏の土用(7月19日〜8月6日)
間日・・・7月21日・22日・26日、8月2日・3日
秋の土用(10月20日〜11月6日)
間日・・・10月21日・29日・31日、11月2日
まとめ
土用は「季節の変わり目」を意味する雑節の一つで、この期間は土いじりをしてはいけないという話は、現代でも言い伝えられています。
しかし実際は、気にしないで土いじりをしても大丈夫です。
仕事でも家庭でも、土や地面に関することをやっても何も悪いことは起きないのです。
ただ、昔の人々が土用の期間に体調を整え、次の季節の仕事に備えていたという歴史は忘れてはなりません。
便利なものが増え、昔よりもずっと過ごしやすくなった現代人ですが、季節の変わり目は体を労ることを心がけていきましょうね。
