秋の七草の種類一覧!意味や覚え方と春の七草との違いとは?
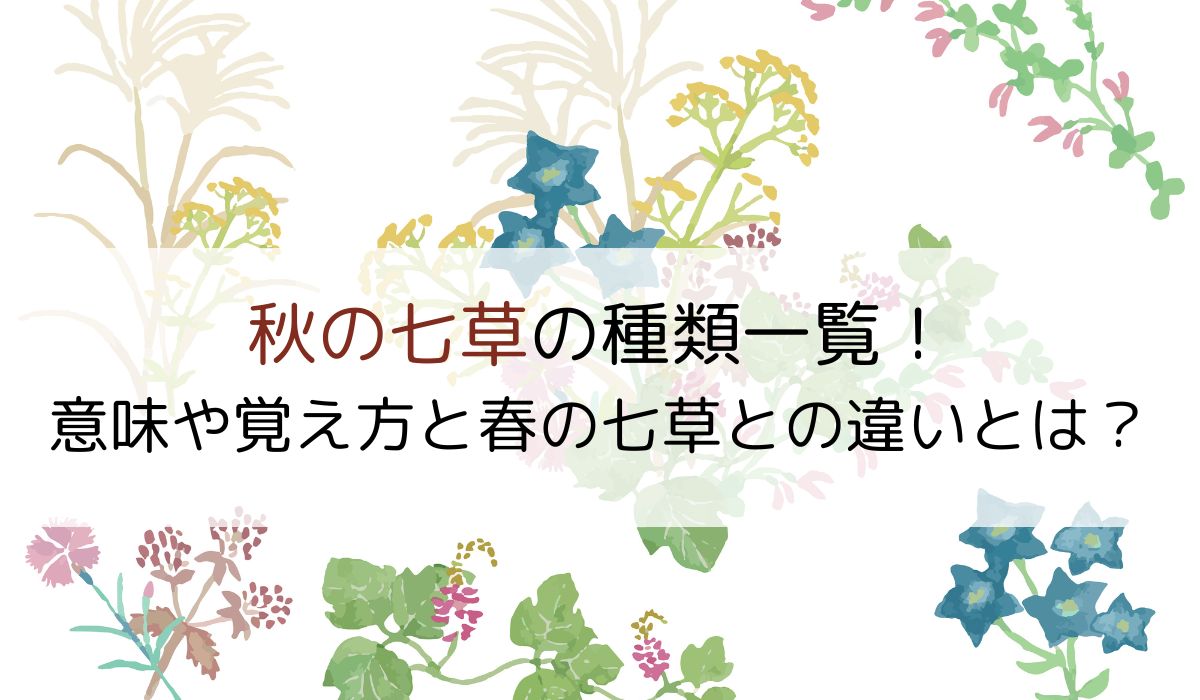
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
みなさんは、秋の七草の種類を全部言えますか?
そもそも、秋の七草ってなんなのでしょうか?
今回は、秋の七草の意味や覚え方をご説明いたします。
春の七草との違いも調べていきましょう。
秋の七草の種類一覧

秋の七草がある意味は「花を観て、季節の到来を楽しむ」ということが目的です。
- 萩(はぎ)…1cm程度の赤紫色の花。マメ科。
- 尾花(おばな)…ススキのこと。
- 葛(くず)…円筒状に小さな花が群生する様に咲く。
- 撫子(なでしこ)…秋の七草では日本固有種のカワラナデシコのこと。
- 女郎花(おみなえし)…小さな黄色い花をたくさん咲かせる。
- 桔梗(ききょう)…星型の青紫色の花。白色や桃色もある。
- 藤袴(ふじばかま)…5mm位の小さな花が房の様に咲く。現在絶滅危惧種。
秋の七草の意味と由来は?
秋の七草は全て野花であり、それらが咲く野原を昔は「花野(はなの)」と言いました。
秋の七草がは「花を観て、季節の到来を楽しむ」ということが目的。
昔の日本人には花野を散策して短歌や俳句を詠むという楽しみがあったのです。
秋の七草の由来は、奈良時代の歌人である山上憶良(やまのうえのおくら)の2つの和歌が由来とされており、これらは万葉集に記されています。
〈山上憶良の和歌〉
・その1
秋の野に 咲きたる花を 指(および)折り かき数(かぞ)ふれば 七種(ななくさ)の花
意味は、秋の野に咲いている花を指折り数えると7種類あったよ・・・というほのぼのした雰囲気の和歌ですね。
・その2
萩の花 尾花(おばな)葛花(くずばな) なでしこの花 女郎花(おみなえし)また藤袴 朝貌(あさがお)の花
意味は、秋の七草はこんな種類の花ですよ・・・と紹介してくれている和歌となっています。
朝貌とは、諸説ありますが「桔梗」のことを指していると言われています。
ちなみに、山上憶良は貴族ではありましたが、仏教や儒教に関心がありました。
その影響か、家族の愛や社会的な優しさ、位の低い者の貧困や素朴さに視点を向けた和歌を詠む、当時は異彩を放つ万葉歌人であったのです。
万葉集には山上憶良の和歌が78首も選ばれており、著名であることが頷けます。
ですから、奈良時代以降の人々が万葉集に載っている山上憶良の上記2つの和歌を読み、「秋の七草はこうなのだな」となっていったと考えられますね。
秋の七草の覚え方は?
1、頭文字で覚える
頭文字での覚え方は、「お好きな服は」です。
秋の七草の最初の文字をとって組み合わせ、文にしてしまったものです。
お…オミナエシ
す…ススキ
き…キキョウ
な…ナデシコ
ふ…フジバカマ
く…クズ
は…ハギ
2、五・七・五・七・七のリズムで覚える
下記を呪文の様に唱えて覚える方法です。
語感とリズムが良いため、日本人であれば簡単に覚えられますね。
「ハギキキョウ クズフジバカマ オミナエシ オバナナデシコ アキノナナクサ」
春の七草との違いとは?
秋の七草と春の七草の違いは、そもそも「目的」自体が違います。
春と秋ということで、まるで対の様に存在はしているのですが、実は由来も全く違うのです。
またそれぞれの植物の種類も用途が違っています。
秋の七草
ハギ、キキョウ、オバナ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ
秋の野原に咲く野花をみて、秋を感じるというものです。
万葉歌人の山上憶良(やまのうえのおくら)の和歌が由来しています。
ちなみに秋の七草は、ススキ以外は薬効成分があるとされています。
春の七草
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ
1月7日の「人日(じんじつ)の節句」に、邪気払いや体調を整える意味を込め、その年の健康を祈って七草粥を食べる風習のこと。
中国の無病息災を願う風習と、古代日本のお正月に若菜を摘んで食べる風習、朝廷行事の7種の穀物のお粥で五穀豊穣を願う行事が合わさったものが由来とされています。
まとめ
秋の七草は、「ハギ、キキョウ、オバナ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ」で、奈良時代の歌人である山上憶良の和歌が由来とされています。
春の七草の様に七草粥を食べて邪気払いや健康を祈るという意味ではなく、秋の野に咲く花を鑑賞し、季節の到来を楽しむという意味が秋の七草にはあります。
秋の野原を鑑賞するという行いは、コンクリートが多くなった街や忙しい現代人には、ちょっぴり難しいことかもしれません。
しかし河原や道端にも目を配ったり、少し足を伸ばして自然を求めれば、秋の七草を見つけることができるかもしれませんよ。
今年の秋は万葉歌人 山上憶良の純朴な和歌を思い出し、七草を探してあなたも秋を感じてみませんか?
