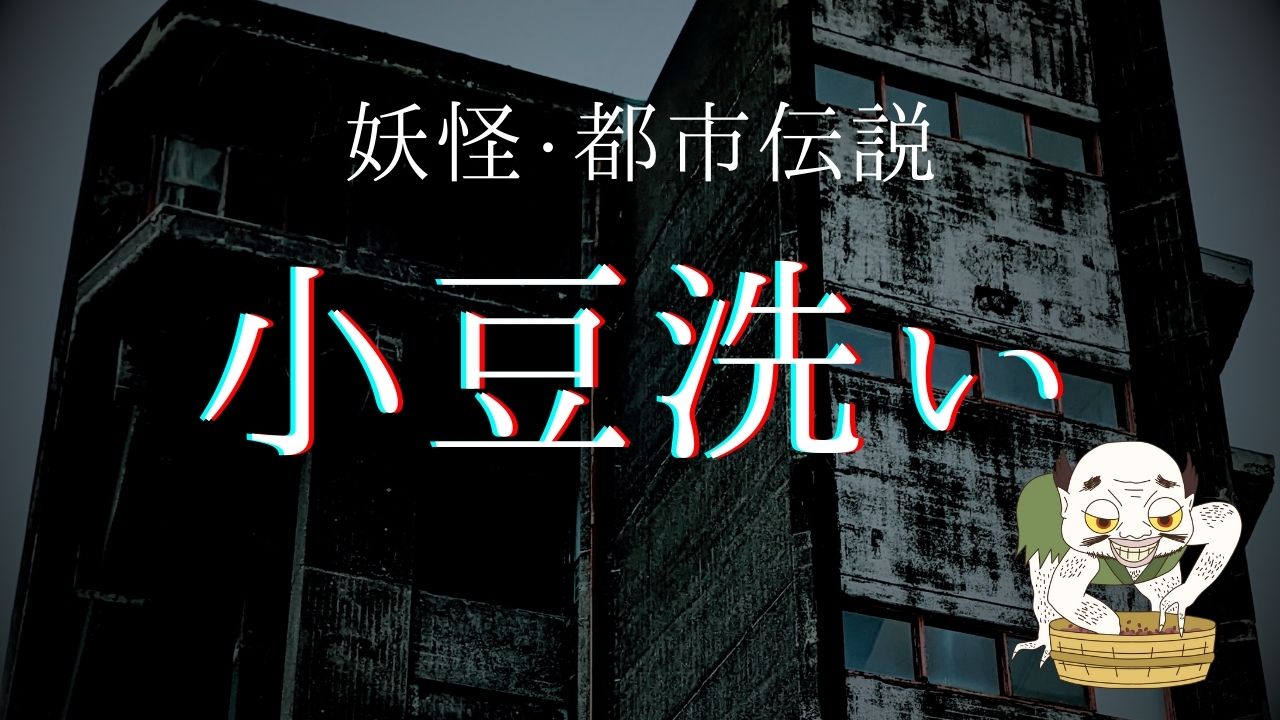※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
アニメや映画などでその存在を知られている「小豆洗い」という妖怪についてご紹介していきます。
「小豆洗い」はアニメなどで見たことがある人も多い妖怪ではないでしょうか。
今回は「小豆洗い」の名前の由来や正体、なぜ小豆を洗うのかという詳細な部分までしっかりとご説明いたします。
「小豆洗い」とはどんな妖怪?

「小豆洗い」とは、全国各地に伝承として古くから伝わる妖怪です。
読み方は「あずきあらい」で、一般的に使われている「小豆(あずき)」の読み方と同じなんですよ。
川などの水辺で「小豆とごうか、人とって食おうか」と歌を歌いながら小豆を洗い、そのショキショキという洗う音で人間を誘い出して崖などに落としてしまうという、実はとても怖い妖怪なんです。
その姿は老婆の姿をしていると伝わっている地域もあれば、姿は見ることが出来ないが小豆を洗う音だけ聞こえる妖怪として伝わっている地域もあり様々なんですよ。
確かに姿形はないのにショキショキという音だけが聞こえていたら気になって見に行ってしまいますよね。
「小豆洗い」の名前の由来
川辺でたらいなどに入った小豆を洗っている姿がそのままその名前になったという説が一番有力視されています。
地域によっては「小豆とぎ」などとも呼ばれ、またその見た目が老婆として伝わっている場合は「小豆洗い婆」などの名前で伝わっていることもあるんですよ。
「小豆洗い」の正体
小豆洗いの伝承が伝わる地域でその正体として伝わっているのは「狐や狸などが化けた姿」だというものです。
狐などは稲荷神社に代表されるように神の使いとも言われていますよね。
小豆も古くから神聖な食べ物とされており、祭事に食べられることが多い食材でした。
そんな神聖な小豆を洗うというのは「神様の使い」である使役動物の役目とされていましたが、時代が進むごとに神様への信仰が薄れていき、神の使いであった動物たちがそのまま妖怪となってしまった。
というのが小豆洗いの正体として有力視されている説なんですよ。
「小豆洗い」はなぜ小豆を洗うの?
小豆は古来よりその赤い見た目から神聖な食べ物として使われきました。
そんな神聖視されている小豆を静かに洗う、という行為によってより人間に恐怖感を与えるために小豆を洗っていると言われています。
まとめ
映画などではどこかコミカルに描かれていた小豆とぎですが、実は人をがけ下などに落としてしまう怖い妖怪だったんですね。
小豆を研ぐだけで実害はないと思っている人も多いのではないでしょうか。
実は地域によっては「女性がその姿を見ると良縁に恵まれる」など縁起の良い妖怪として伝わっていることもあるんですよ。