「張子の虎」は縁起物?由来や置き場所はどこがいい?
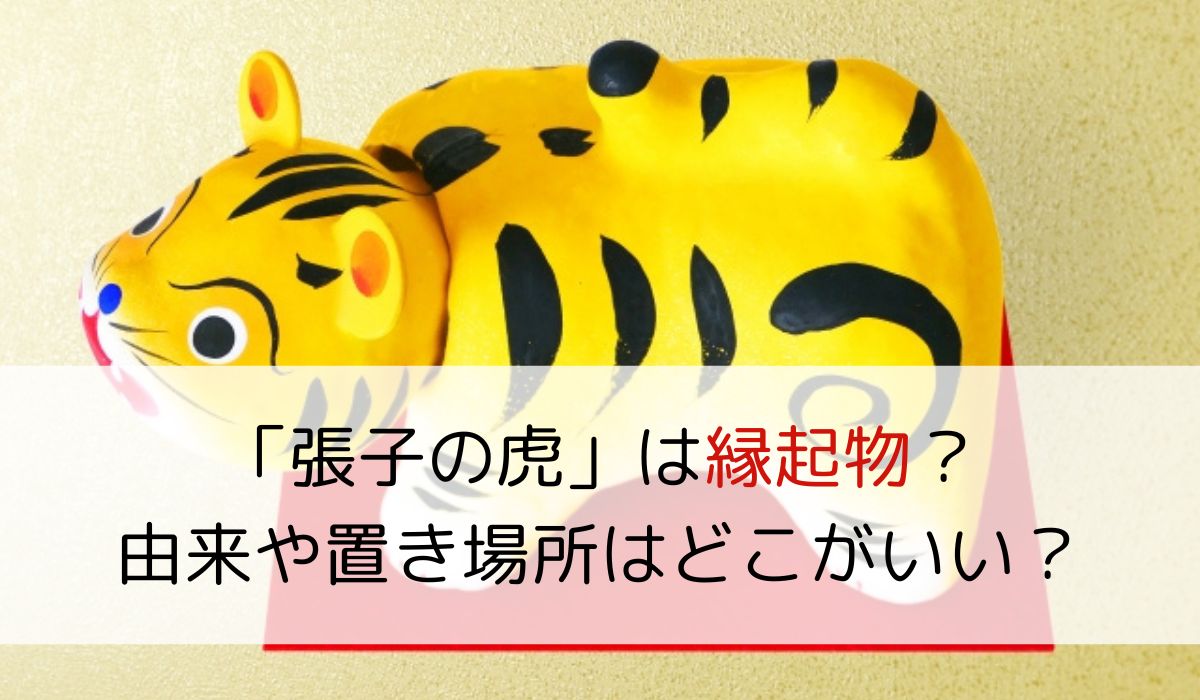
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
張子の虎(はりこのとら)ってご存知ですか?
首がゆらゆら揺れる、勇ましくもちょっと可愛らしさのある虎の置き物です。
今回はその張子の虎は縁起物なのか、由来や置き場所はどこがいいのか等について勉強していこうと思います。
張子の虎は縁起物?

「張子の虎」は、主に端午の節句に男児の健やかな成長や出世を祈願するために飾られる縁起物の一つです。
「はりこのとら」と読みます。
主に端午の節句に男児の健やかな成長や出世を祈願する意味で、江戸時代頃から玩具や工芸品として飾られるようになりました。
虎という生き物は、ご存知の通り強く勇猛果敢、子育ても一生懸命行う生命力の強い猛獣です。
ですから、虎のように強く逞しく、愛情深い男子に成長して欲しいという意味が込められています。
さらに張子の虎には八方睨みで邪気を払う効果もあるとされており、魔除けの意味もあると言われています。
加えて「虎は千里行って千里帰る」という諺があることから、武運を祈る意味でも縁起物として扱われているのです。
以上の理由から張子の虎は縁起物として重宝されているのです。
張子の虎の由来とは?
張子の虎のルーツは、中国にあります。
古代中国で人々は虎を神獣として崇拝していました。
これを虎王崇拝と言います。
実際中国には虎が生息していますから、人々はその強さと生命力に神々しさを感じたのでしょう。
一方、中国から虎という文化を伝えられた日本には、虎は生息していません。
ですから日本では「異国にしか存在しない神獣」として扱ったと言われています。
ちなみに、日本人が生きた虎を見たとされているのは、江戸時代であったと言われています。
それまでは中国東北地方や朝鮮半島などから贈られたり運ばれてきた、虎の皮や頭蓋骨を見るくらいだったのです。
しかも当初は虎の皮は貴族だけが扱えるものであり、武士たちが縁起を担いでこぞって虎の皮を使用し始めたのは中世になってからでした。
そして江戸時代になると見世物小屋文化も広まりますから、やっと庶民の間にも「虎」というものが認識され始めたのです。
その結果、縁起物として張子の虎が作られるようになったり、絵などにもたくさん描かれるようになっていったのです。
ちなみに、江戸当時は「ヒョウ」も虎として見世物に出されていました。
なんとヒョウは、虎の雌であると思われていたようですね。
見世物小屋などで見られるとなると、人々はこぞって出かけるほど虎は人気でした。
虎はその力強さから庶民でも縁起物とされ、一目見るだけで悪病にかかる心配がなくなると言われていたそうです。
張子の虎を置くならどこがいい?
張子の虎は縁起物ですので、普段置いておくのなら、他の縁起物と同様に扱うと良いでしょう。
清潔なところで、人が多く集まる場所や、玄関が適しています。
特に玄関はおすすめで、張子の虎が八方睨みで玄関からの邪気や悪運を追い払ってくれるという効果があると言われています。
ただし、玄関に置く場合には大切なポイントがあります。
それは、虎を左右どちらに置くかということです。
これは風水学的な考え方なのですが、玄関から入ってきた気は反時計回りに回ると言います。
よって、虎の置物は玄関から見て右側に置くと良いと言われています。
悪い気が玄関から入った途端に虎がやっつけてくれるという構図になる訳です。
そしてこの時、必ず虎の顔を玄関に向けるようにしましょう。
虎は西の方角の守護神
虎は、西の方角の守護神でもあります。
これは神話と風水が合わさったお話なのですが、虎は500年生きると神獣 白虎になると言い伝えられているからです。
ですから、白虎は西を守護しているので、張子の虎も西の方角に置くと良いということになります。
そしてもちろん、端午の節句になれば、普段飾っている玄関から皐月人形のそばに張子の虎を移動して飾ってもかまいません。
縁起物は、置く場所をきれいにして大切に飾るという気持ちが重要ですので、あまり気負わずに飾るようにしてくださいね。
張子の虎以外の縁起物にご興味のある方は、こちらもぜひおすすめです。
>>招き猫の左手と右手の意味と違いは?色によっても違うの?
>>七福神の並び方にルールや順番はある?横並びや2列の時は?どこに置くといい?
赤べことの違いは?

赤べことは、張子と虎と同じように首がゆらゆら揺れる赤い牛の郷土玩具です。
「べこ」とは牛のことを指すので、赤べことは赤い牛という意味になります。
赤べこは福島県の会津若松市で作られていた歴史があり、「厄除けの牛」「幸運の牛」と人々から親しまれてきた縁起物の一つでもあります。
張子の虎との違いは、見て分かる通りモチーフが「虎」と「牛」というところです。
さらに由来も違っており、張子の虎が神獣扱いで生まれたという由来に対し、赤べこは
- 「赤い牛が疫病を払った」
- 「大地震で被害を受けた地域の再建で労働に使った黒牛は倒れたが、赤牛は倒れなかった」
という様な身近な雰囲気の由来からできたものだというところです。
また張子の虎は、端午の節句に飾るという風習がありますが、赤べこはそんな風習はありません。
さらに張子の虎には、中が空っぽの構造から「去勢を張る人」、首を振る特徴から「ただうなずいているだけの人」といった皮肉のある言い回しをされるということもありますが、赤べこは人を例える様な言い回しはありません。
このようにどちらも張子であり、首を振るという特徴がそっくりなので混同しがちですが、全くの別物なのです。
ただどちらも縁起物であることは間違いありません。
まとめ
張子の虎は厄除けなどの縁起物であり、中国から伝わった虎という生き物が神獣扱いされ、その生命力の強さにあやかって生まれた伝統工芸品、郷土玩具だということがわかりました。
そして端午の節句には虎のように強くたくましい子になるようにと飾られる風習があります。
張子の虎の置き場所としては、玄関、人気の多いリビングなどにに飾ると良いとされています。
ちなみに、張子の虎とよく似た動きをする赤べことは、由来などは全く違います。
しかしどちらも縁起物であるので、両方飾ってみても良いのかもしれませんね。
