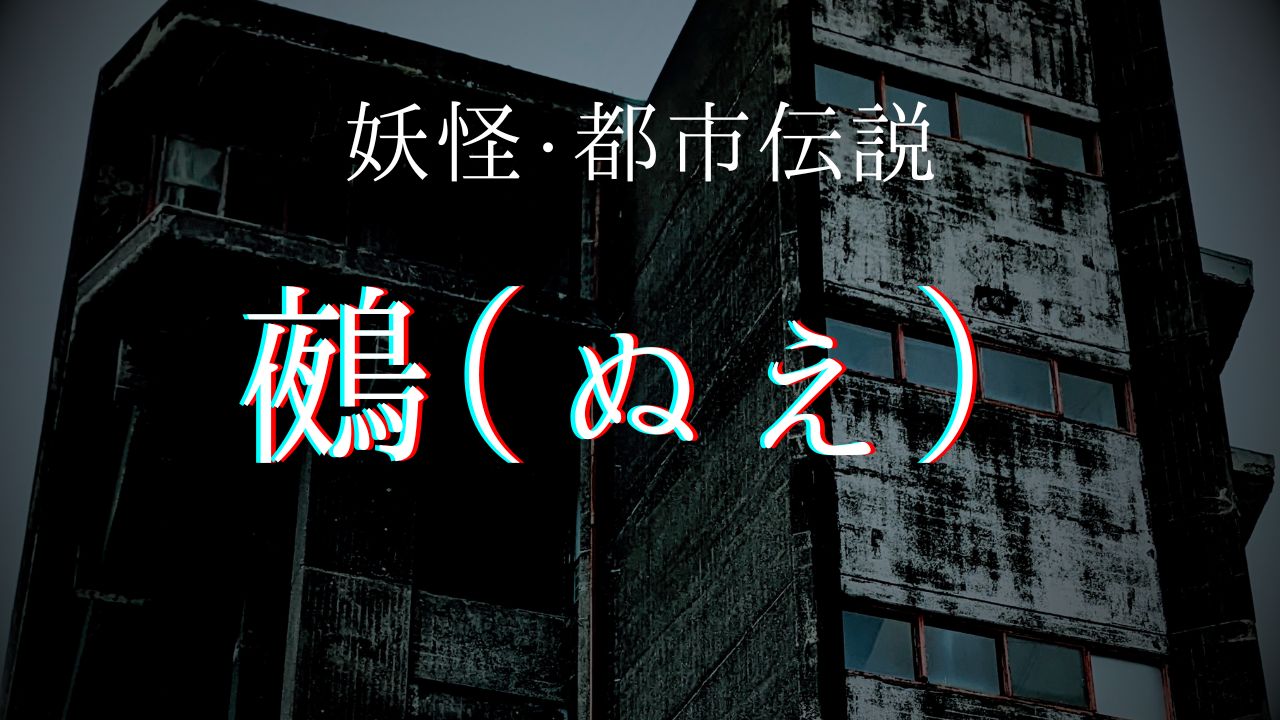※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
妖怪「鵺(ぬえ)」とは、平安時代後期からその名が知られている妖怪です。
「鵺(ぬえ)」は得体のしれないものとして書物に書かれる事が多く、またその表記の違いも書物によって様々です。
今回は、妖怪「鵺(ぬえ)」とは?名前の由来や正体は?について解説いたします。
「鵺(ぬえ)」とは

「鵺(ぬえ)」とは、顔は猿、胴体は狸、手足はトラといったキメラのようにつぎはぎの体をしており、「ヒョウヒョウ」という鳴き声で鳴くとされている妖怪です。
平安時代末期に近衛天皇の御所に毎夜姿を現し、その鳴き声で天皇を悩ませ源頼政の手によって退治されたと、平家物語にも書かれています。
悲し気な鳴き声は平安時代の人々の不安をあおり、鳴き声が聞こえると「何事も起きないように」と祈祷をするほどだったんですよ。
「鵺(ぬえ)」の名前の由来
鵺が近衛天皇を苦しめたという話が記載されている「平家物語」において、「その声はぬえのようだった」と記載されていたことから、その名が一般的に広まったとされています。
また鵺という漢字をよく見ると「夜」と「鳥」という漢字に分かれることがわかります。
実際に夜に鳴くという特徴を持つ「トラツグミ」という鳥は平安時代から存在しており、貴族たちはその鳴き声を「不吉な事が起こる前触れ」と恐れていたんだそうです。
この事から「トラツグミのような鳴き声を出す怪異」を「鵺」と呼ぶようになったんだとか。
「鵺(ぬえ)」の正体は?
正体に関しても諸説囁かれており、はっきりとした正体は判明しておりません。
ですが、鵺の鳴き声に似た声で鳴く
- 「トラツグミ」という鳥である
- 狸に似た体と狐のような尻尾、虎のような鋭利な爪を持つ「レッサーパンダ」である
という説があるんですよ。
鵺について書かれている「源平盛衰記」の中で、まさに背中が虎で足が狸、尻尾がキツネとして鵺の姿が描かれている事から、一致する点が多いということで「レッサーパンダなのではないか」という説となっています。
ただ、平安時代からレッサーパンダが居たのかという点については疑問が残りますので、あくまでも一つの説として捉えるのが賢明です。
まとめ
その姿は書籍によって様々ですが、複数の動物を組み合わせたような姿で描かれることが多いのが鵺という妖怪なんですね。
由来となったトラツグミは本州や四国、九州でその姿を見ることができます。
北海道では夏に飛来してくる渡り鳥として知られているんですよ。