ラジオ本放送の日(7月12日の記念日)|今日は何の日
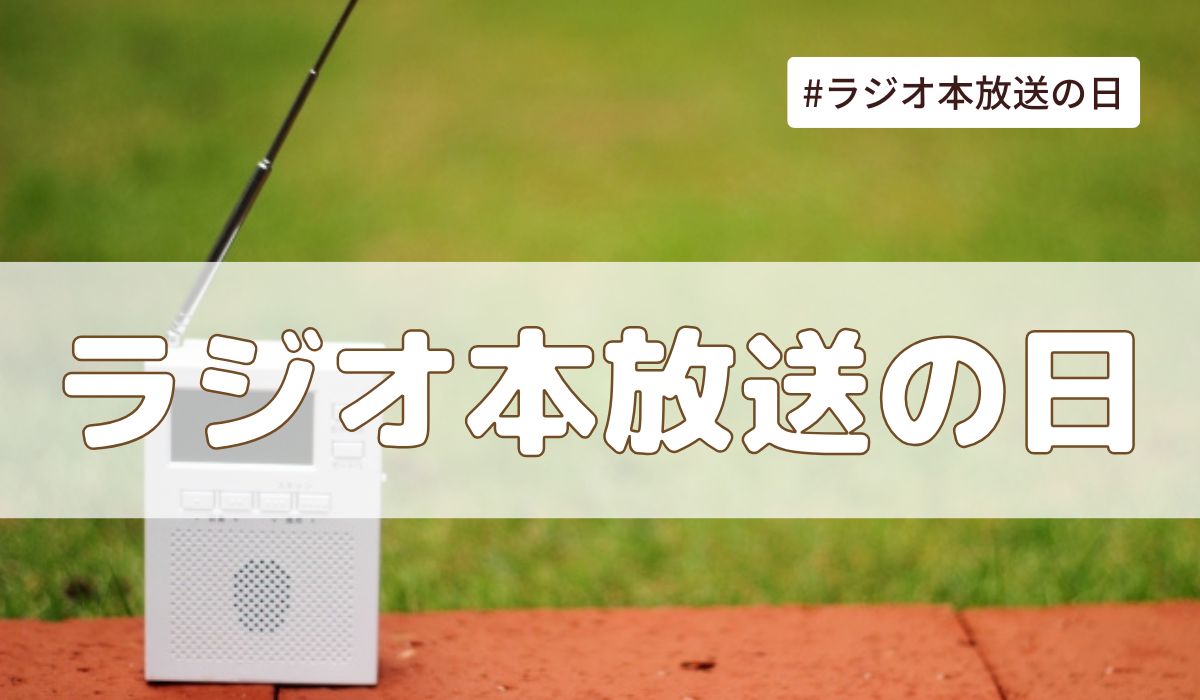
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
7月12日は「ラジオ本放送の日」です。
この日は、1925年(大正14年)7月12日に、東京放送局(現・NHK)による日本初のラジオ本放送が開始された日です。
今回は7月12日の「ラジオ本放送の日」について解説いたします!
合わせて読みたい▽
7月12日は何の日?記念日・誕生日・歴史・花言葉まとめ【今日は何の日】
「ラジオ本放送の日」(7月12日の記念日)

1925年(大正14年)7月12日に、東京放送局(現在のNHK)が愛宕山からラジオの本放送を開始した日です。
この日を記念し、7月12日が「ラジオ本放送の日」に制定されました。
それ以前、3月22日の試験放送(仮放送)が行われていましたが、この7月12日の正式スタートが、今につながる「声の公共メディア」時代の幕開けとなりました 。
試験放送でのアナウンサーの第一声
当初のアナウンサーによる第一声は
「JOAK、JOAK、ジェー、オーゥ、エーィ、ケーィ、こちらは東京放送局であります。」
でした。
「JOAK」とは東京放送局のコールサイン(呼び出し符号)で、無線局の識別ができるようにするためのものです。
当時の受信契約数は約3,500件、1日の放送時間は約5時間。受信料は月額1円(当時の大卒初任給は50~60円程度)でした。
ラジオといえば無料で聞けるもの、というイメージがありますが、同時は受信料が必要だったんですね。
愛宕山からの中継
本放送は、東京・愛宕山(現在の港区)に設けられた送信所から行われました。
標高約26メートルで、23区内でも高台に位置し、電波が市街を広くカバーできる場所として選ばれました。
現在では、NHK放送博物館として記念施設が設置されており、放送当時の資料を見学することができますので、お子さんと見学に行くなんていうのもいいかもしれませんね。
ラジオ本放送の歴史的意義
ラジオによる「音声を通じた情報提供」が可能になったことで、災害・ニュース・娯楽などに対応できるようになりました。
1923年の関東大震災を機に無線放送の必要性が強まり、2年後には本放送開始に至りました 。
現代でも災害用にラジオが聞けるものを準備しているご家庭も多いですよね。
インターネットが普及した今でも、ラジオによる情報収集は活用されています。
まとめ
今ではパソコンやスマホなどでラジオを聞く人も増えていますね。
声だけのラジオは作業をしている時にもちょうどよく筆者もたまに聞いています。
ラジオ本放送の日を機に、人々に定着したラジオの良さをもう一度感じてみるのもおすすめです。
合わせて読みたい▽
>>【7月12日】人間ドックの日とは?由来・意味・健康を見直す一日に

