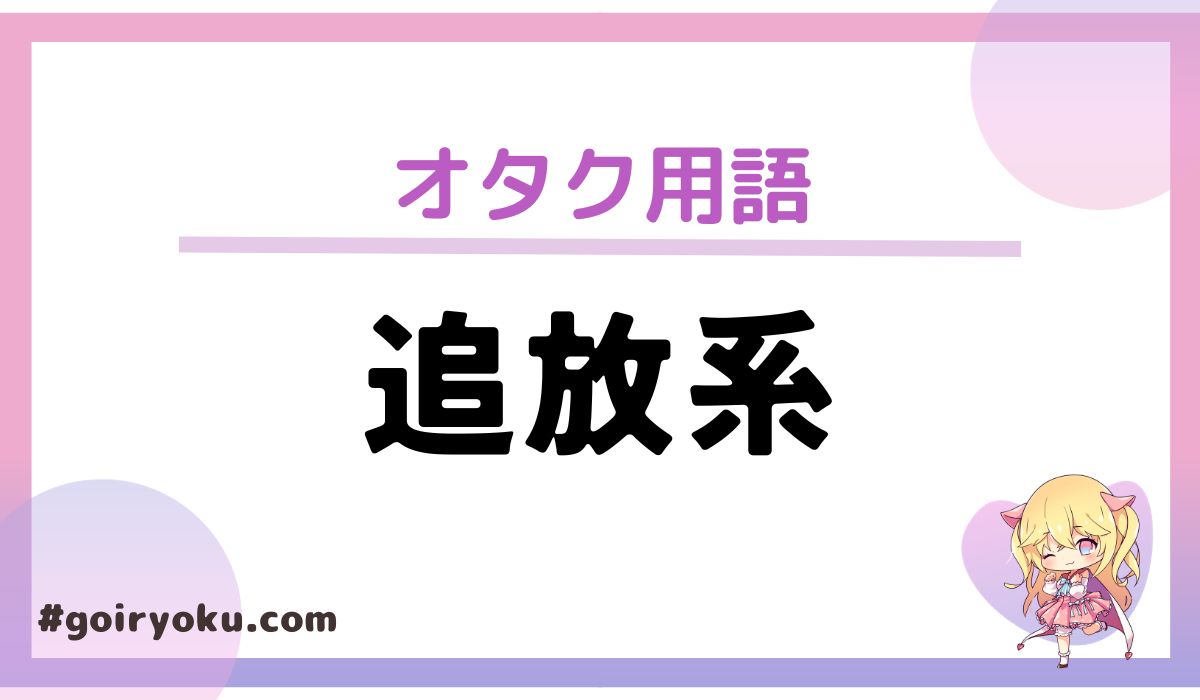※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
作品ジャンルの1つとして使われている「追放系」という言葉をご存じでしょうか。
なろう系などと並び人気のジャンルですが、その意味を知らないという人も多いかと思います。
今回は「追放系」について意味はもちろん、元祖と呼ばれる作品やおすすめ作品、最近は多すぎる?などの疑問にもお答えしていきます。
目次
「追放系」とは
「追放系」とは漫画や小説のストーリー展開におけるジャンルの1つです。
「ついほうけい」と読みます。
その名の通り、主人公が「戦闘能力がない」などの理由で勇者パーティを追放されてしまうところから始まり、その後輝かしい道へと進む主人公と、主人公を追放したことで徐々に崩壊していってしまうというストーリーが王道と言われています。
勇者パーティに属していた時は不当な扱いを受けていたりと不運だった主人公が、自分の能力を開花させてくれる人物と出会うドラマティックなストーリー展開と
主人公によって受けられていた恩恵に気づかず追放した勇者パーティが破滅していく胸がスカッとするような喜びを同時に楽しむことが出来ると人気の作品ジャンルなんですよ。
「追放系」の元祖作品は?
様々な説がありますが追放系の元祖と呼ばれているのが「真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました」という小説作品です。
「小説家になろう」という自作小説投稿サイトから生まれた作品で、追放系作品の元祖にして頂点と称されている作品です。
小説版・漫画版2つの合計売上が100万部を突破し、2021年にはアニメ化もされています。
ライトノベルファンだけではなく一般の読者層も虜にしている事がわかりますね。
「追放系」のおすすめ漫画は?
「Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ」
勇者召喚という技で異世界に召喚された主人公ですが、能力の低さから森の奥へと追放されてしまいます。
そこでレベルが1つ上がりレベル2となった主人公はたくさんの魔法が使えるようになり、本領発揮。
自分の名前と姿を変えてこの世界で生き残ることを決意した主人公と、その強さを認めて妻となる奥さんの可愛さの恋愛模様も楽しめる作品です。
(2025/07/14 17:36:06時点 Amazon調べ-詳細)
「勘違いの工房主 英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話」
SSランクのパーティを「戦闘の役に立たない」とクビになったクルトですが、実はすさまじい「クラフト能力」を持っていました。
壁はどんなに広大でも3時間程度で完全補修、料理を作れば完全回復は当たり前と一般的なクラフトスキルよりはるかにすごい能力でした。
そのクラフト能力が当たり前になってしまい、ありがたさを見失ってしまった英雄パーティの絶望への転落も見事に描かれた作品です。
(2025/07/14 17:36:07時点 Amazon調べ-詳細)
「追放系」最近多すぎる?
なろう系の作品ジャンルの1つともいわれる追放系は、最近ではその数もどんどん増えてきています。
人気の設定という事もありますが、あまりに増えすぎたことにより供給が需要を追い越してしまい、人気も落ち着いてきているように感じられます。
長いタイトルが特徴的で、目につきやすいのも「多すぎる」と言われてしまう1つの原因なのではないでしょうか。
まとめ
長いタイトルに、書店で一度は手に取ったという人も多いのではないでしょうか。
「多すぎる」とは言われていますが人気ジャンルであることに違いはありませんので、異世界物やスカッとするお話を読みたいと考えている人はぜひ挑戦してみてくださいね。