梅干しが縁起物と言われる意味は?なぜ引き出物に選ばれるの?
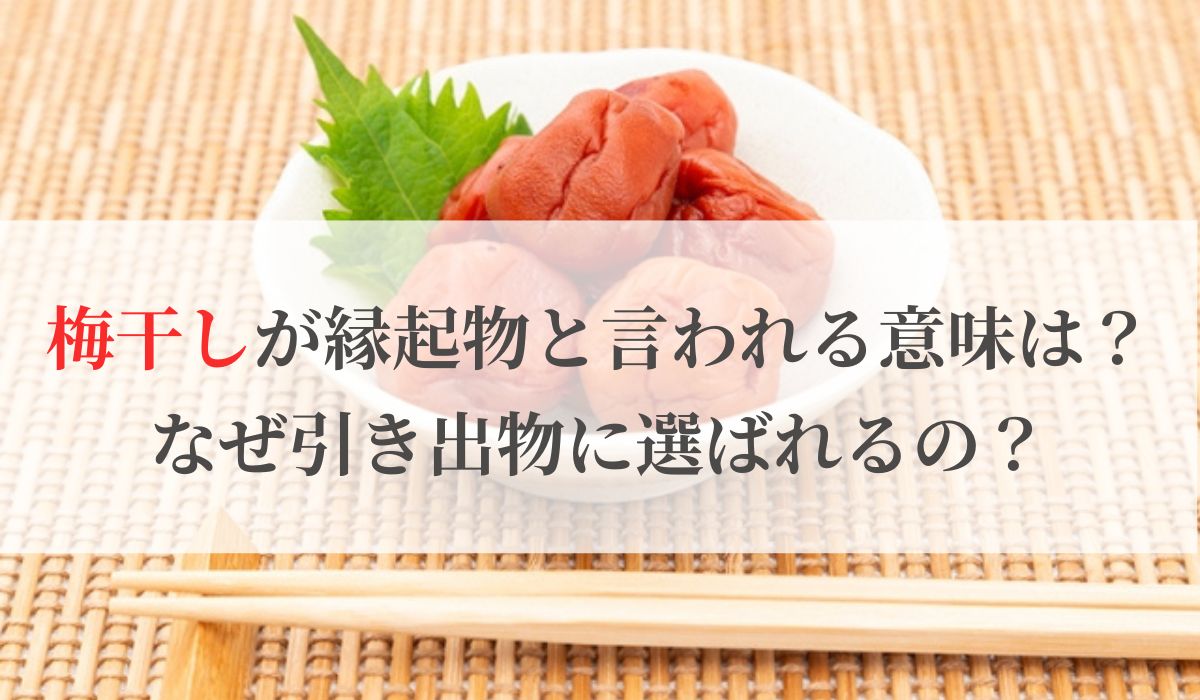
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
梅干しは日本人であれば誰でも食べたことがあるでしょう。
ご飯のお供としてだけではなく、梅干しは縁起物として扱われていますよね。
今回は、梅干しが縁起物と言われる意味や、なぜ引き出物に選ばれるのかを探っていきましょう。
日本の伝統的食べ物「梅干し」の秘密に迫る一記事です。
合わせて読みたい▽
>>昆布が縁起物である理由は?香典返しもO??送る意味や由来も解説
目次
梅干しが縁起物と言われる意味や由来6つ

由来1:梅は長く生きる木であることから、健康長寿を意味するため。
由来2:梅は他の花より真っ先に花を咲かせることで春を告げる木と言われており、それにちなんで成功や幸福を呼び込むと言われているため。
由来3:梅の花は香りも高く、赤や白い花をつけることが紅白で縁起も良いため。
由来4:梅干しのシワの多い外観が、まるで長く生きた様であることから、長寿、夫婦円満を連想させるため。
由来5:梅干しには厄除けの意味もあるため。ことわざにも「梅はその日の難逃れ」というものがあることから。
由来6:梅という字の右側「毎」という文字には、象形文字として「女性」という意味があり、子孫繁栄とかけられているため。
このように、梅干しが縁起物である意味とその由来には、梅という木の特性や文字、そして梅干しにまつわる逸話が多くあることがわかりました。
ちなみに、縁起物で有名な言葉である「松竹梅」にも梅は入っています、
梅は幸先の良いものであると再認識できますね。
>>「松竹梅」のランクの順番は?意味やその上、その下もあるの?
梅干しが引き出物に選ばれる理由

梅干しは、主に祝い事である慶事に使われる引き出物です。
梅干しが引き出物に選ばれる理由を下記にまとめみました。
・理由1:縁起物であるため
春を告げる梅の木の生命力の強さや、厄除け、梅干しの外観が長寿・夫婦円満を連想させることから
・理由2:保存がきく
すぐには食べなくても腐らない、常温保存が可能な利便性から
理由3:日本人の食卓に合っている
普段の食卓、お弁当、お米でもお粥でもどのような状況にも日本人の食卓に合っているから
理由4:調理食材としても汎用性がある
梅肉和え、ドレッシング、お肉に挟んで揚げる・・・など梅干しは調理方法やアレンジ方法たくさんあることから
理由5:贈られる側の年齢や性別を問わない
好き嫌いはあれど、老若男女誰でも食べても良い食材であることから
理由6:引き出物としての汎用性が高い
個包装なら軽量に、反対にまとめれば重さを出すことも可能
色々な状況に合わせてスタイルをかえ、引き出物として活用できることから
以上のことから梅干しは、日本人の食文化に深い歴史を持つ食べ物であり、色々な工夫もできる食材で、保存も効いて年齢を問わず好まれるため、引き出物として重宝することがわかりました。
梅干しは、誰が貰っても困らない食べ物の代表の一つなのかもしれませんね。
同じような理由で鰹節も昆布も引き出物としてなかなかに重宝する様ですよ。
もしご興味がある方がいらっしゃったら、こちらの記事もどうぞ。
ちなみに、今時の引き出物はバームクーヘンも人気ですので、こちらもリンクに貼らせていただきます。
>>バームクーヘンが縁起物とされる意味や由来は?個包装は縁起が悪い?
注目!「申の年の梅」とは?

さて、梅干しを引き出物として扱うなら、忘れてはいけないのが「申の年の梅」です。
申年の梅は「申梅(さるうめ)」と呼ばれ、「去る」という言葉と掛けられて「悪いものが去る」という言い伝えがあるからです。
ですから「無病息災」「厄除け」などのご利益的な意味で好まれているのです。
ちなみに由来は、平安時代の天穂4年(960年)の申年に、村上天皇が疫病に臥したところ、申年に収穫した梅干しと昆布茶によって体調が回復したことからだと言われています。
12年に一度しかない申年の梅は、大切な人への贈り物として、また自身家庭への幸福祈願として珍重されているのです。
まとめ
梅干しが縁起物として言われる理由には、梅という木自体に縁起の良い魅力と特徴があり、そして梅干しのシワが長い年月を連想させることから長寿や夫婦円満などの意味を持つことがわかりました。
梅干しがなぜ引き出物に選ばれるのかというと、上記の縁起の良い意味の他に、日本人の食卓に合うことや、汎用性なども加味されて人気があるのです。
グローバル化した現代では、色々な食文化も我々の身近なものになっています。
そのためか梅干しの需要は近年では減少傾向にありますが、やはり日本人として伝統的な食品である梅干しの魅力、今こそ見直してみませんか?
合わせて読みたい▽
>>鰹節が縁起物なのはなぜ?引き出物に選ばれる理由や由来とは?
